東洋思想研究の安岡正篤先生の書を何年も何年もかけて読んでいます。年を重ねて腑に落ちる事も少しずつ出てきましたが、まだまだ未熟者、言葉はすっと出てこないし体現なんて遠く及ばない。でも、何回か読み返すとあ、こう言う事かと気付きにで会えるとまた一つ人としての深みが出せる様になった気にもなります。
先生の茶のお話の中に、苦味の中に甘味がある。甘味のある苦味でなければ本当の苦味ではない。とありました。
甘味は単純で誰でも分かると思いますが、苦味を良く思えるには苦味の中の味を理解できるように意識していかなければならない。
その事に気付いて味付けにも活かせればと思う様になりました。
山菜の走りのふきのとう。

天ぷらにするとそうでもないですが湯がいただけではかなりの苦味があります。でも、味噌や砂糖で味を補うと苦味の先に渋みや甘味とあとは春の優しい香りが嬉しいです。
タラの芽

太い茎の部分を大振りに天ぷらにすると歯切れの良い食感にみずみずしさと苦味とほのかな甘味が楽しいですね。湯がいた時には醤油と胡麻で油分も加えてとても食べやすくなります。
今季は山菜入りコースもチャレンジしました。

たけのこの土佐煮、ウドの酢味噌和え、イタドリの油炒め、コシアブラバターソテー、花わさび醤油漬け、ふきのとうのピクルス・・・など調理してて色んな発想が浮かんできてとても楽しかったです。
山菜の期間がとても短くて5月上旬で終わりになりました。手ごたえもあったので来季以降も続けていきます。
そしていよいよ鮎の季節が始まります。

繊細微妙な味わいはとても奥が深く年々扱う度に興味の尽きない食材です。
鮎の魅力もお伝えできればと思います。
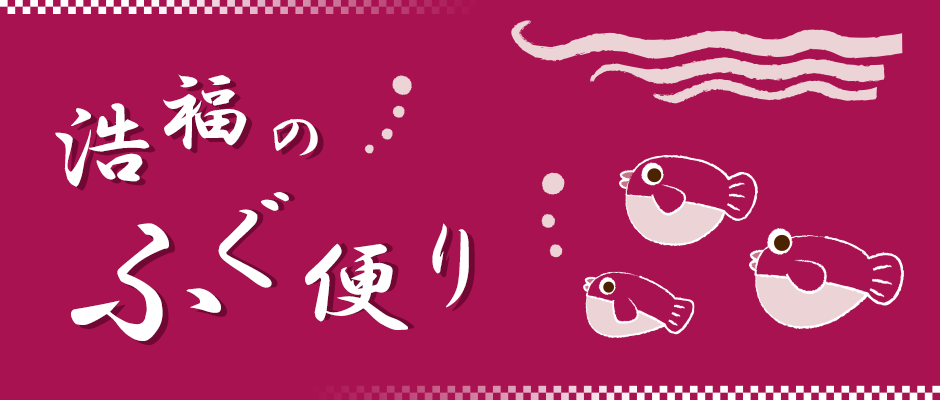
コメント